【松原昌洙が解説】共有名義不動産のトラブル回避大作戦!基礎知識
【松原昌洙が解説】共有名義不動産のトラブル回避大作戦!
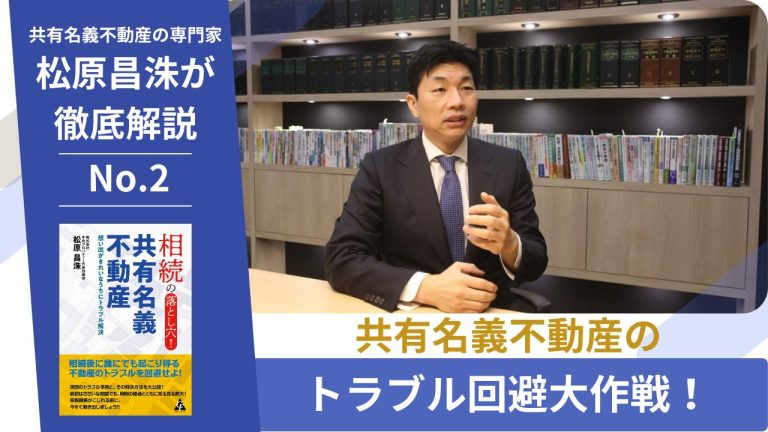
目次
前回の記事では、相続トラブルを招きやすい「共有名義不動産」についてご紹介しました。
今回は、トラブルを招かないための事前対策を解説していきます。
【Amazonで販売中】相続の落とし穴!共有名義不動産: 想い出がきれいなうちにトラブル解決
知っておこう!不動産相続時の遺産分割の流れ
土地や建物などの不動産を複数人で相続した場合、どのように分ければよいのでしょうか?
まずは、不動産の遺産分割の流れを見ていきましょう。
ー遺産分割協議で分割方法を確定しよう
遺産分割協議とは、相続するすべての遺産の分割方法を決める話し合いのことです。
相続人全員で行うもので、全員の同意がなければ成立しません。
また、たとえ遺言書がある場合でも、遺産分割協議によって、別の分割方法が提案され、全員が合意した場合は、その内容が優先されます。
ー相続から3年以内の相続登記を忘れずに!
遺産分割協議が決着したら、決着した分割方法を記載し、共有者全員が記名押印した「遺産分割協議書」を作成しましょう。
遺産分割協議書は、相続登記の際に必要になります。
相続登記とは、不動産の登記名義人を、相続した共有者に名義変更することです。
これまで、相続登記に期限はありませんでしたが、令和6年4月1日から、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。
相続登記の手続きは誰でもできますが、時間がかかる上に煩雑なため、専門家に相談することをおすすめします。
不動産相続で揉めないための3つの事前対策
相続で起こるトラブルの大半は、共有名義不動産によって起こります。
揉めないための事前対策として、「共有関係をつくらない」対策をとりましょう。
生前贈与と遺言書
生前贈与とは、生きている間に推定相続人へ贈与することです。
ただし、生前贈与には贈与税がかかることを覚えておきましょう。
贈与税をできるだけ抑えながら贈与するには、専門家の力が必要です。
また、遺言書をつくり、不動産の名義を“単独所有”とする分割方法を指定しておくことで、相続後に共有名義不動産となることを回避できます。
家族信託
家族信託は、財産を信頼できる家族に託すことで、「共有」状態になるのを回避する有効な方法の一つです。
財産を家族信託すると決めた本人(例:父)が、家族の誰か(長男)を指名し、財産の継承と管理を任せる信託契約を交わします。
家族信託を開始した瞬間に、財産は信託財産となります。
これで、いざ相続となった際にも、共有状態になることを回避できます。
揉めないために共有物の民法ルールを知っておこう
共有名義不動産は共有者全員で所有している不動産なので、独断で売却したり、大きな変更を加えることはできません。
ここでは、共有名義不動産の共有のルールをご紹介します。
共有物の管理にあたって、以下の3つを覚えておきましょう。
- 単独でできること
- 過半数の同意でできること
- 共有者全員の同意が必要なこと
「単独でできること」の一つに、「自己持分の売却」があります。
例えば、共有名義の不動産を売却したいけれど、反対する共有者がいる場合、不動産全体の売却には全員の同意が必要ですが、自己持分のみであれば、共有者の同意なく売却できます。(民法第206条)
「過半数の同意でできること」は、管理行為や賃貸契約などです。
この場合の「過半数」は、共有者の人数による過半数ではなく、持分比率のことです。
「共有者全員の同意が必要なこと」には、解体、建築などの大規模な変更、不動産全体の売却などが含まれます。
このように、共有物の管理ルールは民法で定められていますので、共有者の一人が勝手に変更行為や管理行為を行うことは認められていません。
共有名義を解消する6つの方法
共有関係になってしまった後でも、できる対策があります。
ここでは、共有関係を解消するための6つの方法をご紹介します。
- 全体を売却する
- 持分を売却する
- 持分を移転する
- 持分を放棄する
- 土地を分筆する
- 共有物分割請求訴訟をする
1.全体を売却
共有者全員が合意の上で、不動産全体を売却します。
売却後は、持分比率に応じて、売却金を共有者で分配します。
ただし、反対する共有者や、音信不通の共有者がいたりすれば、売却は難しくなります。
2.第三者に持分を売却
自分の持分だけを、自分だけの意思で第三者に売却する方法です。
ただし、全体売却による分配金よりも、減価されるのが一般的です。
また、第三者に持分が移ったことで、他の共有者と揉めるケースもあるので注意しましょう。
3.共有者間で持分を売買
共有者間で持分の売買を行い、共有関係を解消する方法です。
ただし、安い価格で売買すると贈与と見なされることもあるので、取引金額の設定には気をつけましょう。
4.持分放棄
持分を放棄し、ほかの共有者に譲る方法です。
見返りを一切求めずに手放すことになるので、もっとも選ばれにくい方法といえるでしょう。
5.現物分割
一つの土地を、共有者全員できっちり区分けして分筆登記する方法です。
ただ、土地は持分比率通りに面積を分けたとしても、各土地の価値も比率通りになるとは限りません。
そのため、専門家に依頼する必要があるでしょう。
6.共有物分割請求訴訟をする
裁判所に共有物分割請求訴訟を申し立てることで、裁判所に分割方法を決めてもらい、共有関係を解消することができます。
メリットは、最終的に必ず何かしらの方法で分割できることです。
デメリットは、裁判所の判断となるため、必ずしも自分の希望の分割方法になるとは限らないことでしょう。
まさに最終手段といえる方法なので、できればこれまでの5つの方法のどれかで決着させたいところです。
まとめ
相続トラブル回避のために、今すぐやるべき対策は見つかりましたでしょうか?
次の記事では、実際にあったトラブルの相談をご紹介します。
具体的な事例を通して、より実践的な知識を身につけていきましょう。

この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。




