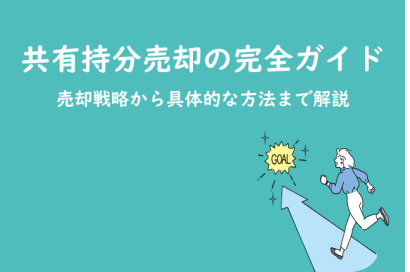共有持分売却の完全ガイド|売却戦略から高額売却のコツまで徹底解説
共有持分売却の完全ガイド|売却戦略から高額売却のコツまで徹底解説

目次
「共有持分を売りたいけど、何から始めればいいか分からない…」
そんな悩みを抱えるあなたへ。この記事では、共有持分売却の基礎知識から、具体的な売却戦略、そして高額売却を実現するための裏技まで、余すところなく解説します。
不動産会社の選び方、売却後の注意点など、売却を成功させるための重要ポイントを網羅。
この記事を読めば、共有持分売却に関する不安を解消し、最適な方法でスムーズな取引を進めることができるでしょう。

共有持分の売却に共有者の同意は不要
共有名義の不動産を売却する場合、共有者全員の同意が原則必要です。共有者の一人が反対する場合、不動産全体の売却はできません。
一方、共有持分とは、共有者が不動産全体に対して持つ権利の一部を指します。この共有持分のみを売却する場合、他の共有者の同意は不要です。(民法第206条)
例えば、兄弟3人で共有名義の家を所有している場合、家全体を売却するには共有者全員の同意が必要です。しかし、自分の共有持分のみを売却する場合、他の共有者の同意は不要です。
また、共有持分を売却することで、以下のようなメリットがあります。
- 共有者間のトラブルから解放される
- 現金化できる
- 税金の負担から解放される
- 子や孫の相続トラブルを回避できる
共有持分売却の最大のメリットは、煩わしい共有者同士のトラブルから解放されることです。
共有持分の売却を売却する方法
共有持分を売却する具体的な方法は、以下の3つです。
- 共有者間で持分を売買する
- 買取業者に持分を買い取って貰う
- 仲介業者を経由して持分の買い手を探して貰う
共有者間で持分を売買する
共有者間で持分を売買することは、共有持分売却の最もシンプルな方法の一つです。
第三者が介入しないため、仲介手数料など売却に掛かる費用も抑えることができます。
ただし、持分を買い取る側に資金力があることが前提となります。売買価格をめぐって折り合いがつかないケースが多いため、交渉が難航しやすい特徴があります。
買取業者に持分を買い取ってもらう
専門の買取業者に共有持分を買い取ってもらうことも可能です。
この方法のメリットは、共有者の同意を得る必要がなく、速やかに現金化できる点です。
ただし、買取価格は市場価格よりも安くなる傾向があります。
また、買取業者の中には悪質な業者も存在するため、持分の売却後に他の共有者とトラブルになるケースがあります。信頼できる業者かどうか、よく見極める必要があります。
仲介業者を経由して持分の買い手を探してもらう
不動産会社などの仲介業者に依頼し、共有持分の買い手を探してもらう方法です。
共有持分は、一般市場で買い手を見つけることが非常に難しいとされています。かと言って、専門の買取業者に売却すると市場価格よりも安い価格で売却することになります。
仲介業者を経由する方法は、仲介業者独自のネットワークを活用して販売活動を行うため、買い手が見つかりにくい持分でも、好条件=高値で売却が可能です。
ただし、大手不動産会社や街中の不動産は、持分のみの売却サポートを行っていないケースが多いため、共有持分専門の仲介業者に依頼する必要があります。

共有持分の買取相場はいくら?
あくまで目安ですが、共有持分の買取価格は、市場価格の3割〜5割程度になることが多いようです。
ただし、これはあくまで一般的な目安であり、個別のケースによって大きく変動する可能性があります。
以下は、共有持分の買取相場に影響する内容の一例です。
- 共有持分割合
- 不動産の種類(土地、戸建て、マンション、アパートなど)
- 不動産の所在地
- 共有者の数
- 不動産会社の査定方法
正確な買取価格を知るためには、複数の不動産会社に査定を依頼し、比較検討することをおすすめします。
共有持分を高額売却するための3つのコツ
市場価格よりも、安くなりがちの共有持分ですが、以下3つのポイントを押さえることで高額売却が期待できます。
- 持分割合を増やしておく
- 買取業者よりも仲介業者を選ぶ
- 売却にかかる費用を抑える
1.持分割合を増やしておく
共有持分を高く売るためには、持分割合を増やすことが有効です。
持分割合が大きいほど、共有不動産に対する権利が強くなり、購入希望者にとって魅力的な物件となるため、高値で売却できる可能性が高まります。
他の共有者から持分を買い取る、贈与を受けるなどして、持分割合を増やしておくことを検討しましょう。
2.買取業者よりも仲介業者を選ぶ
共有持分専門の買取業者は、迅速な現金化が期待できる一方で、買取価格が市場価格よりも低くなる傾向があります。
より高値での売却を目指すのであれば、不動産仲介業者に依頼し、高値で買ってくれる買主を探すのがおすすめです。仲介業者は、市場動向や売却ノウハウに精通しているため、より良い条件での売却をサポートしてくれます。
3.売却にかかる費用を抑える
共有持分売却にかかる費用には、仲介手数料、登記費用、税金などがあります。これらの費用を抑えることで、手元に残る金額を増やすことができます。
仲介業者の中には、売主からの手数料を貰っていない不動産会社もあります。
複数の仲介業者に見積もりを依頼し、手数料を比較してみると良いでしょう。
センチュリー21中央プロパティーは売却にかかる諸費用が0円 ≫
共有持分の売却の流れ
共有持分の売却の流れは、以下の通りです。
- 共有者に持分を売却することを伝える
- 市場価格を調べる
- 各社に査定を依頼する
- 最低売却価格を決める
- 販売活動開始
- 売買契約締結
- 決済・移転登記
共有持分の売却は、他の共有者の同意なしで可能ですが、後々のトラブルを避けるために可能であれば、事前に共有者に通知しておくことがおすすめです。
また、不動産会社へ査定を依頼する前に不動産の市場相場を確認しておくことで、不動産会社の言いなりにならずに済みます。
但し、共有持分の購入希望者は少ないため、自分の希望する額での売却が難しい場合も大いにあります。
最低限いくらであれば妥協できるかも、自分の中で想定しておくと良いでしょう。

共有持分売却時の必要書類
共有持分の売却には、主に以下の書類が必要です。
- 登記識別情報
- (持分を売却する人の)身分証明書、印鑑証明書、住民票、実印
- 固定資産税評価額の証明書
- 土地測量図及び境界確認書(土地の場合)
詳しくは、不動産会社に確認しましょう。
共有持分売却に伴う費用と税金
共有持分を売却する際には、一般的に以下のような諸費用がかかります。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 登記費用
- 譲渡所得に関する税
仲介手数料
不動産会社に仲介を依頼して共有持分を売却する場合、仲介手数料が発生します。
仲介手数料は、売買契約成立時に不動産会社へ支払う費用で、一般的には、売買価格の3%に消費税を加えた金額が上限となります。
不動産会社によっては、売主の仲介手数料が無料の会社もあるので、確認しましょう。
印紙税
不動産売買契約書を作成する際には、印紙税がかかります。
印紙税は、契約書に貼る印紙の種類によって金額が異なり、契約金額に応じて定められています。印紙税は、契約書作成時に支払う必要があります。
登記費用
共有持分を売却した際、所有権を移転するために登記費用がかかります。
これは、法務局に名義変更を申請する際に支払う費用で、登録免許税と司法書士への報酬が含まれます。登録免許税は、固定資産評価額に一定の税率を乗じて計算され、司法書士報酬は依頼する事務所によって異なります。登記費用は、売買代金や不動産の評価額によって変動します。
登記費用は、買主が負担してくれる場合もありますので、不動産会社に確認してみましょう。
譲渡所得に関する税
共有持分を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額で、所有期間によって税率が異なります。
所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税率は長期の方が低くなります。譲渡所得税は、確定申告によって納める必要があります。
共有持分売却後のトラブルに注意
共有持分は、他の共有者の同意なしで売却できますが、次のようなリスクがあります。
- 他の共有者との関係性が悪化する
- 持分を購入した買取業者と他の共有者がトラブルになる
- 共有物分割請求訴訟に発展する可能性がある
他の共有者との関係性が悪化する
共有持分の売却は、他の共有者の同意なしに行うことができます。
しかし、事前に共有者に売却の意向を伝えていなかった場合、共有者間の関係性が悪化する可能性があります。
共有者としては、売却された事実を知った際に「なぜ事前に相談してくれなかったのか」「知らない人と共有関係になっていて不安」といった感情を抱くことがあります。
とは言え、共有者が多い場合、相続により今後さらに権利関係が複雑になっていくことや自由に不動産を活用できる見込みがないことから、早めに共有関係を解消するのが賢明な判断と言えるでしょう。
持分を購入した買取業者と他の共有者がトラブルになる
買取業者は、共有持分を買い取った後、他の共有者の持分も買い取ろうと交渉する場合があります。
これは、他の共有者の持分を買取業者がすべて買い取り、単独名義の不動産にした状態で、転売しようと考えているためです。
悪質な買取業者の場合、強引でしつこい交渉を繰り返したり、勝手に共有不動産に侵入したりして、共有者とトラブルになることがあります。
共有物分割請求訴訟に発展する可能性がある
持分を取得した業者や個人が、他の共有者に対して「共有物分割請求訴訟」を起こす可能性があります。
共有物分割請求訴訟では、裁判所が共有不動産の分割方法を決定します。
分割方法としては、
- 現物分割:不動産を物理的に分割する
- 換価分割:不動産を売却し、売却代金を共有者間で分割する
- 代償分割:共有者の1人が他の共有者の持分を買い取る
などがあります。
共有物分割請求訴訟は、時間と費用がかかるだけでなく、「持分を勝手に売ったアイツのせいだ!」と持分を売却した人に怒りの矛先が向くケースもあり得ます。
トラブルなく共有持分を売却するには?
共有持分をトラブルなく売却するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 共有持分専門の業者に相談する
- 弁護士のサポートを受ける
- 売買契約書の内容を正確に理解してから契約締結する
共有持分専門の業者に相談する
共有持分の売買は、一般的な不動産売買とは異なり、専門的な知識や経験が必要です。共有持分専門の不動産業者は、共有関係の調整や法的な手続きに精通しており、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。
共有者間の調整や権利関係の整理を代行してくれるため、トラブルなく共有持分を売却するためには、共有持分の取り扱いに慣れた不動産会社のサポートを受けましょう。
弁護士のサポートを受ける
共有持分の売買は、法的な問題が絡むケースも少なくありません。弁護士は、共有持分の売買契約書の作成や確認、権利関係の整理、紛争解決など、法的な側面からサポートを提供してくれます。
特に、共有者間で意見が対立している場合や、複雑な権利関係がある場合には、弁護士のサポートが不可欠です。弁護士に相談することで、法的なリスクを回避し、安心して取引を進めることができます。
また、売却後に共有者とトラブルになった場合も、法的な視点で対処方法を助言してもらえるため心強いパートナーと言えるでしょう。
売買契約書の内容を正確に理解してから契約締結する
売買契約書は、共有持分の売買における権利義務関係を明確にするための重要な書類です。契約書の内容を十分に理解せずに契約を締結すると、後々トラブルに発展する可能性があります。
特に共有持分の場合、売却後のトラブルに注意が必要です。
契約書の内容は、専門用語が多く、複雑な条項が含まれている場合があります。そのため、契約書の内容について疑問に思う点や不明な点があれば、セカンドオピニオンも検討しましょう。必ず専門家(不動産業者や弁護士)に相談し、曖昧なまま契約することは避けましょう。
共有持分売却のよくある質問
Q.共有持分を高く売るコツはありますか?
共有持分を高く売るには、共有持分専門の不動産業者に依頼することが大切です。
不動産会社の中でも、買取業者ではなく、仲介業者へ依頼する方が、高値で売却できる可能性が高いです。
また、不動産鑑定士の鑑定書付きがあれば、買い手が見つかりやすく高額売却ができます。
Q.自分の持分のみを売却することは可能でしょうか?
自己持分は、共有者の同意なく売却可能です。(民法第206条)
共有名義不動産全体の売却が難しい場合、自己持分のみの売却を検討するとよいでしょう。
Q.共有持分はいくらで売れますか?
共有持分の売却価格は、不動産全体の売却と比べると低くなります。
また他の共有者が住んでいるなど、利用状況や立地条件によっても大きく変動します。
少しでも高値で売却したい場合は、当社の不動産鑑定士による無料査定サービスをご利用ください。
Q.共有持分を売却した後、他の共有者はどうなりますか?
持分の売却後は、持分の購入者と他の共有者が、共有状態になります。
購入者によっては、他の共有者に持分の売買に関する交渉を持ちかけることがあります。無理な交渉は、共有者間でのトラブルに発展します。
売却後のトラブルを防ぐためにも、売却先は慎重に選ぶことが大切です。
Q.持分売却の手続きはどう進めるのがよいですか?
持分の売却手続きは、共有持分専門の不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。通常の不動産と比べて、権利調整が複雑なため、専門業者に依頼しなければ、後々共有者とのトラブルになりかねません。
Q.他の共有者が住んでいても持分を売却できますか?
可能です。
他の共有者とトラブルにならないように、弁護士と連携しながら、慎重に売買手続きを行います。
Q.持分を売却する際に費用はいくらかかりますか?
共有持分の売却時には、仲介手数料や譲渡所得税などがかかるのが一般的です。
当社では、売主様から仲介手数料はいただいておりませんので、0円で持分の売却をサポートいたします。売却を迷っている方も、まずはご相談ください。
まとめ
共有持分の売却は、他の共有者の同意なしで可能です。
センチュリー21中央プロパティーは、共有持分専門の不動産仲介会社です。
共有名義不動産に詳しい弁護士が常駐しているため、共有者とトラブルを抱えている場合や売却後のトラブルが不安な方にも、ご安心いただける体制が整備されております。
弁護士相談費用や仲介手数料など、売却にかかる諸費用は0円です。
- 共有者と不仲で関係を解消したい
- 不動産の活用ができていない
- 共有者が多すぎる
- 固定資産税を負担したくない
共有名義不動産でお悩みの方は、一度当社へご相談ください。

この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。